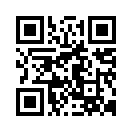2012年02月02日
日本語ボランティア養成講座第10回目「聞くことを教える」
先週の日曜日(1月29日)日本語ボランティア養成講座ブラッシュアップ編第10回目を開催しました
ブラッシュアップ講座は、今既に日本語支援ボランティア(日本語ができなくて困っている外国人の方に日本語を教えるボランティア)として活動をしている方を対象に、日本語を教える技術に更なる磨きをかけてもらおうと企画した講座です
10回目の講座の講師は城保江先生。「音声教育」について教えていただきました

まずはじめに、受講者の方からの音声に関する質問に答えていただきました。
皆さん、日本語の「ん」には発音の種類によって5つものグループがあることを知っていましたか どれも同じに聞こえますが、発音するときの舌の位置などで微妙に音が違うそうです。では突然ですがここで問題。次の言葉を発音して、「ん」の発音が同じグループを5つ作ってみてください
どれも同じに聞こえますが、発音するときの舌の位置などで微妙に音が違うそうです。では突然ですがここで問題。次の言葉を発音して、「ん」の発音が同じグループを5つ作ってみてください
1.サンマ、 2.感動、 3.三角、 4.親愛、 5.パン、6.真ん中、7.順位、8.サンバ、9.三円、10.金庫、11.散歩、12.ペン、13.漫画、14空き缶
ヒント :5グループとは、①[m]のグループ、②[n]のグループ、③[ŋ]のグループ、④母音の直前の「ん」、⑤語末の「ん」です。答えが知りたい方は、SPIRA(info@spira.or.jp)までいつでもどうぞ
:5グループとは、①[m]のグループ、②[n]のグループ、③[ŋ]のグループ、④母音の直前の「ん」、⑤語末の「ん」です。答えが知りたい方は、SPIRA(info@spira.or.jp)までいつでもどうぞ
また、受講者の方からは他にも、「おとうさん」は「otouさん」と「う」と書くのに、何故「お」と発音するの 、「きっぷ」をどうしても「きぷ」と発音してしまう学習者には、どうその違いを説明したらいいの
、「きっぷ」をどうしても「きぷ」と発音してしまう学習者には、どうその違いを説明したらいいの といった質問がありました。普段何も意識しないで使っている日本語ですが、外国語としてみると分からないことがたくさんですね。城先生の丁寧な解説はとても勉強になりました
といった質問がありました。普段何も意識しないで使っている日本語ですが、外国語としてみると分からないことがたくさんですね。城先生の丁寧な解説はとても勉強になりました
今回の講座では、「音声教育」の中でも特に聴解(聞き取り)の指導の仕方を中心に教えていただきました。聴解能力を鍛えるためには、もちろんできるだけ長く対象言語に触れさせる時間を取ることが重要ですが、ただ聴かせるだけでなく、聴解のコツ・ストラテジーを学習者に身に付けてもらう指導をすることが大切です。
今回の講座では、聴解の授業を「前作業(聞く前の作業)」、「本作業(テキストを数回にわたって聞いて理解する)」「後作業(聞いた後に反応を表現したり、テキストから言語を学んだりする)」に分け、聴解のストラテジーを身に付けてもらうためにそれぞれの段階においてどのような授業の工夫ができるかを参加者の皆さんに考えていただきました。
模擬授業のお題は「台風のニュースを聞く」。今回は3グループに分かれて授業のデモンストレーションをしてもらいました。



参加者の皆さんには、音声教材として使用する「台風のニュース」を元に、「前作業(聞く前の作業)」としてどのような授業ができるかを考えてもらいました。
「前作業」としては4つの重要なガイドラインがあります。
①テキストの内容について学習者が持っている知識や情報、経験を引き出す。
②テキストに関連した絵や写真を利用して、内容を予測させる。
③キーワードを確認する。
④聞く前に質問を与え、聞き取りの目的を意識させる。
参加者の皆さんには、このガイドラインに沿って、日本列島の地図を用意したり、キーワードをカードにまとめたり、「台風が来たらどうなりますか?」「あなたの国にも台風は来ますか?」「どんなことに注意しなければいけませんか?」といった質問を考えたりしてもらいました。絵を見せたり、小道具を使ってどのような内容かを推測させたり、質問の仕方を工夫することでキーワードを引き出しやすくしたりと、それぞれのグループが工夫を凝らした模擬授業をされていて、とても勉強になりました






「本作業」「後作業」の授業のガイドラインが知りたい方はSPIRA(info@spira.or.jp)までご連絡ください
また、先生には催眠マジック( )もしてもらいました。まず足を肩幅に開いて目を閉じます。そして右手をのばします。そして次の様にイメージします。
)もしてもらいました。まず足を肩幅に開いて目を閉じます。そして右手をのばします。そして次の様にイメージします。
「あなたの手がどんどん、どんどん、にょきにょき、にょきにょき伸びていきます。どんどん伸びて壁を突き抜けて建物の外に出てしまいました。手はまだまだ伸びていきます。天山を越えて玄界灘まで来てしまいました。にょきにょき、にょきにょき。その先に見えるのは対馬。そして釜山 ソウル~
ソウル~ 」
」
はい、では目を開けて、左手を前に伸ばし左右の手の長さを比べてみてください。右手の方が左手より長くなっていませんか

これは、いかに私たちが思い込みに囚われているかを体験してもらう実験で、「そんなことができるわけがない」と思っていても、イメージを膨らませ、意識を変えることで、自分の思っている以上のことができてしまう体験をしてもらうものです。音声の指導をする際には、学習者さんに、間違いを恐れず、大きな声で、声が壁を突き抜けていくイメージで発声をしてもらうと、聞き取りやすいきれいな日本語に近づけるかもしれません。また、滑舌をよくするためには、ワインのコルクを口の両側にくわえて、話す練習をするとよいそうです。講座でも、受講者の皆さんにコルクの代わりに手をくわえてやってもらいました
城先生、とても楽しい講座をありがとうございました
次回の日本語ボランティア養成講座は2月19日です。
次回のブラッシュアップ講座では、受講者の方だけでなく、日本語教育に携わっている方皆さまに来ていただきたいと思っています
講座では、貞松明子先生に、日本語教育に関する様々な質問に答えていただく予定です。また、前半には「使役形」についてもご教授いただく予定です。
当日のスケジュールは次の通りです。
【日時】:平成24年2月19日(日) 13:00~17:00
【場所】:佐賀県県庁 本館4階正庁
【講師】:貞松明子氏
(前半)13:00~15:00
「使役形」の説明&日本語教育全般に関する質疑応答
(後半)15:00~17:00
日本語教室運営に関する質疑応答(当協会事務局長も出席予定)
参加費は無料です。前半だけ、後半だけ、の参加でも構いません。たっぷり4時間時間がありますので、どんな小さな疑問でもどんどん質問してください。ご興味のある方、ぜひお友達を誘ってお越しください
資料の準備がありますので、ご出席される方は事前に、info@spira.or.jpまで、ご連絡をお願い致します

ブラッシュアップ講座は、今既に日本語支援ボランティア(日本語ができなくて困っている外国人の方に日本語を教えるボランティア)として活動をしている方を対象に、日本語を教える技術に更なる磨きをかけてもらおうと企画した講座です

10回目の講座の講師は城保江先生。「音声教育」について教えていただきました

まずはじめに、受講者の方からの音声に関する質問に答えていただきました。
皆さん、日本語の「ん」には発音の種類によって5つものグループがあることを知っていましたか
 どれも同じに聞こえますが、発音するときの舌の位置などで微妙に音が違うそうです。では突然ですがここで問題。次の言葉を発音して、「ん」の発音が同じグループを5つ作ってみてください
どれも同じに聞こえますが、発音するときの舌の位置などで微妙に音が違うそうです。では突然ですがここで問題。次の言葉を発音して、「ん」の発音が同じグループを5つ作ってみてください
1.サンマ、 2.感動、 3.三角、 4.親愛、 5.パン、6.真ん中、7.順位、8.サンバ、9.三円、10.金庫、11.散歩、12.ペン、13.漫画、14空き缶
ヒント
 :5グループとは、①[m]のグループ、②[n]のグループ、③[ŋ]のグループ、④母音の直前の「ん」、⑤語末の「ん」です。答えが知りたい方は、SPIRA(info@spira.or.jp)までいつでもどうぞ
:5グループとは、①[m]のグループ、②[n]のグループ、③[ŋ]のグループ、④母音の直前の「ん」、⑤語末の「ん」です。答えが知りたい方は、SPIRA(info@spira.or.jp)までいつでもどうぞ
また、受講者の方からは他にも、「おとうさん」は「otouさん」と「う」と書くのに、何故「お」と発音するの
 、「きっぷ」をどうしても「きぷ」と発音してしまう学習者には、どうその違いを説明したらいいの
、「きっぷ」をどうしても「きぷ」と発音してしまう学習者には、どうその違いを説明したらいいの といった質問がありました。普段何も意識しないで使っている日本語ですが、外国語としてみると分からないことがたくさんですね。城先生の丁寧な解説はとても勉強になりました
といった質問がありました。普段何も意識しないで使っている日本語ですが、外国語としてみると分からないことがたくさんですね。城先生の丁寧な解説はとても勉強になりました
今回の講座では、「音声教育」の中でも特に聴解(聞き取り)の指導の仕方を中心に教えていただきました。聴解能力を鍛えるためには、もちろんできるだけ長く対象言語に触れさせる時間を取ることが重要ですが、ただ聴かせるだけでなく、聴解のコツ・ストラテジーを学習者に身に付けてもらう指導をすることが大切です。
今回の講座では、聴解の授業を「前作業(聞く前の作業)」、「本作業(テキストを数回にわたって聞いて理解する)」「後作業(聞いた後に反応を表現したり、テキストから言語を学んだりする)」に分け、聴解のストラテジーを身に付けてもらうためにそれぞれの段階においてどのような授業の工夫ができるかを参加者の皆さんに考えていただきました。
模擬授業のお題は「台風のニュースを聞く」。今回は3グループに分かれて授業のデモンストレーションをしてもらいました。
参加者の皆さんには、音声教材として使用する「台風のニュース」を元に、「前作業(聞く前の作業)」としてどのような授業ができるかを考えてもらいました。
「前作業」としては4つの重要なガイドラインがあります。
①テキストの内容について学習者が持っている知識や情報、経験を引き出す。
②テキストに関連した絵や写真を利用して、内容を予測させる。
③キーワードを確認する。
④聞く前に質問を与え、聞き取りの目的を意識させる。
参加者の皆さんには、このガイドラインに沿って、日本列島の地図を用意したり、キーワードをカードにまとめたり、「台風が来たらどうなりますか?」「あなたの国にも台風は来ますか?」「どんなことに注意しなければいけませんか?」といった質問を考えたりしてもらいました。絵を見せたり、小道具を使ってどのような内容かを推測させたり、質問の仕方を工夫することでキーワードを引き出しやすくしたりと、それぞれのグループが工夫を凝らした模擬授業をされていて、とても勉強になりました

「本作業」「後作業」の授業のガイドラインが知りたい方はSPIRA(info@spira.or.jp)までご連絡ください

また、先生には催眠マジック(
 )もしてもらいました。まず足を肩幅に開いて目を閉じます。そして右手をのばします。そして次の様にイメージします。
)もしてもらいました。まず足を肩幅に開いて目を閉じます。そして右手をのばします。そして次の様にイメージします。「あなたの手がどんどん、どんどん、にょきにょき、にょきにょき伸びていきます。どんどん伸びて壁を突き抜けて建物の外に出てしまいました。手はまだまだ伸びていきます。天山を越えて玄界灘まで来てしまいました。にょきにょき、にょきにょき。その先に見えるのは対馬。そして釜山
 ソウル~
ソウル~ 」
」はい、では目を開けて、左手を前に伸ばし左右の手の長さを比べてみてください。右手の方が左手より長くなっていませんか

これは、いかに私たちが思い込みに囚われているかを体験してもらう実験で、「そんなことができるわけがない」と思っていても、イメージを膨らませ、意識を変えることで、自分の思っている以上のことができてしまう体験をしてもらうものです。音声の指導をする際には、学習者さんに、間違いを恐れず、大きな声で、声が壁を突き抜けていくイメージで発声をしてもらうと、聞き取りやすいきれいな日本語に近づけるかもしれません。また、滑舌をよくするためには、ワインのコルクを口の両側にくわえて、話す練習をするとよいそうです。講座でも、受講者の皆さんにコルクの代わりに手をくわえてやってもらいました

城先生、とても楽しい講座をありがとうございました

次回の日本語ボランティア養成講座は2月19日です。
次回のブラッシュアップ講座では、受講者の方だけでなく、日本語教育に携わっている方皆さまに来ていただきたいと思っています

講座では、貞松明子先生に、日本語教育に関する様々な質問に答えていただく予定です。また、前半には「使役形」についてもご教授いただく予定です。
当日のスケジュールは次の通りです。
【日時】:平成24年2月19日(日) 13:00~17:00
【場所】:佐賀県県庁 本館4階正庁
【講師】:貞松明子氏
(前半)13:00~15:00
「使役形」の説明&日本語教育全般に関する質疑応答
(後半)15:00~17:00
日本語教室運営に関する質疑応答(当協会事務局長も出席予定)
参加費は無料です。前半だけ、後半だけ、の参加でも構いません。たっぷり4時間時間がありますので、どんな小さな疑問でもどんどん質問してください。ご興味のある方、ぜひお友達を誘ってお越しください

資料の準備がありますので、ご出席される方は事前に、info@spira.or.jpまで、ご連絡をお願い致します

Posted by SPIRA at 11:06│Comments(0)
│H23日本語ボランティア養成講座ブラッシュアップ